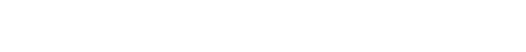1.「新しい ALS 観」―多職種との連携
今まで ALS 患者は発症後 3 〜 4 年経つと呼吸運動系麻痺で多くが亡くなるため、そこまでの期間を視野において、医療・介護を行うというのが「今までのALS 観」でした。しかし現在、人工呼吸器や経菅栄養管理の発達によって、呼吸運動系麻痺を越えて発症から 20 〜 30 年と長期に生活できるようになりました。その間も各種随意運動系の障害が進むので、コミュニケーション障害が生活の中で大きなウエートを占めるようになっています。このように見ると、呼吸運動系麻痺というのは、いわば ALS の終末像ではなく、経過中の部分症状とも考えられます。従って呼吸運動系麻痺を越えた長い経過の病態も視野において、医療・介護を提供する必要があるといった考え方を、東京都立神経病院の前院長であった林秀明先生が「新しい ALS 観」として提唱しました。
在宅療養中の ALS 患者は病気の進行とともに訪問看護師、介護職(ヘルパー)等の手助けが必要になります。在宅療養の場合、自宅に見知らぬ人の出入りが多くなり、他人に多くの日常生活の介助をしてもらうことに、精神的な負担を感じることと思います。しかし、自分でできないことをプロに任せるのは当たり前のことであり、家族介護者の負担を軽減する意味でも、これらの人の援助を積極的に受け入れ、また自身のケアチームを維持していく目的で、積極的に交流を持つように気持ちの切り替えが大切です。
==================================================================
こちらの記事は会員限定です。
閲覧するにはログインをお願いいたします。新規ご登録は下記からお願いいたします。